前回の投稿にて、『廿日合戦の夜に、風が吹いて、一晩で帰っていった』といふ通説は、『関東評定伝』に『同廿四日、大宰府に寄来りて、官軍と合戦す、異賊は敗北す』とあり、廿四日に合戦があったと明記されてゐる事により、神風史観に過ぎないと纏めた。
確かに、「俄かに逆風」「会(たま/\)、夜に大風雨」(『高麗史』)とあるやうに、嵐は吹いてゐる。但しいつ吹いたのかは、記述がなく、わからない。日本滞在中とする説と、撤退中とする説がある。この嵐は台風だとされた事もあるが、この日は太陽暦の11月末に当たり、北部九州に台風が来る可能性は殆ど無い。この季節には例年、強い寒冷前線が通過し、漁船等が転覆する事もある。嵐はさうした異常気象の事だらう。恐らくは、蒙古・高麗軍は日本滞陣中に嵐に遭遇した。元々太宰府陥落が不可能であれば、帰国してもよいとされてゐた。冬になれば北風が卓越し、日本海交通も途絶へがちになって、補給が不安定になる。悪くすれば退路を断たれて全滅である。嵐の通過が帰国を後押しした。
其々が異なる資料に書ゝれてゐた事、即ち廿日の一日で退却といふ神話、怒れる神による蒙古退治譚と、別の史料にあった嵐の記事を簡単に結びつけてゐた。双方の記述は、関連づけられて等をらず、文脈の共通性は無かったし、京都の天気から、廿日の夜に嵐が吹くやうな気圧配置では無かった事も明示できる。
服部英雄氏は、
歴史家は、神の出現こそは嵐の比喩と考えたのであらう。この結合解釈はとても古く、江戸時代には既にさうした像が作られてゐたやうに思はれる。非科学的な思ひ込みであったが、いかにも納得されがちな背景があって、疑はれなかった。
と述べてゐる。
即ち神風史観の骨格を為す、文永の役に於ける、嵐によって一夜で殲滅なるものは、幻想・虚像に過ぎない。けれども信じられやすかった。
尚『元史』洪俊奇(洪茶丘)伝に「冝蠻等島」とあるから、東路軍の将、洪茶丘は西方の今津に向かったと思はれるが、廿日以降であらう。
『勘仲記』十月廿九日条には、「武家あたりは騒動があって、北条六郎と式部大夫時輔が打ち上る、との事だ」と風聞を記してゐる。時輔は北条時宗の異母兄で、二年前の文永九年(1272)の二月騒動で時宗によって殺された筈なのだが、吉野・十津川に逃げてゐるといふ噂があった。北条六郎とは北条教時で、同じく二月騒動にて鎌倉で殺されてゐる。教時は北条朝時の六男だから六郎と呼ばれた。
服部英雄氏は、かう述べてゐる。
従来の説は、六郎は肥前守護となる時定を指すとしてゐたが、彼は時宗政権に忠実だったから、時輔とともに攻め上る筈は無い。
この二名またはその残党が、京都に攻め上ってくるといふ噂があって、『勘仲記』の記主、勘解由小路兼仲は「怖畏きはまり無し」と書いてゐる。鎌倉幕府は国難に一致して対応できない、内紛ばかりだと非難してゐた。朝廷は幕府を非難し、幕府も内部に矛盾を抱へてをり、蒙古襲来への対応に不安な要素はあったが、合戦の最中に露呈する事は無かった。
- ※参考文献
-
- 「服部英雄著 蒙古襲来と神風 ~中世の対外戦争の真実~」
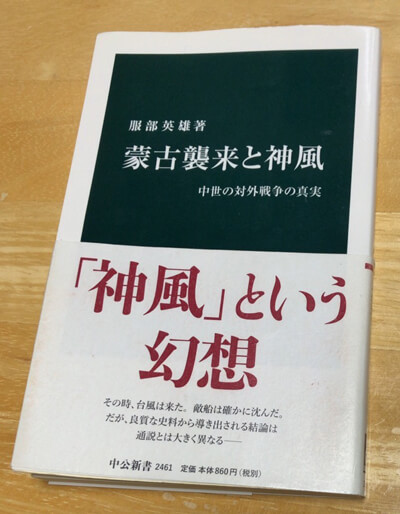
Be the first to comment