前回に引き続き、伊藤仁斎の「命」字の語法を考察する。
明治啓蒙の言説に蘇る荻生徂徠 ~ 伊藤仁斎と荻生徂徠 その一 ~
『命の一字二義あり理を以て言ふものあり、気を以て言ふものあり。天に在てはこれを命と謂ふ、人に在てはこれを性と謂ふ』
(陳淳著 性理字義)
『中庸』の「天命之謂性」の命について、陳淳は斯く言ふ。
「「天の命、これを性と謂ふ」「五十にして天命を知る」「理を窮め、性を尽し、命に至る」といふがごとき、これらの命の字は皆これ専ら理を指して言ふ。」と。性理学(朱子学)では、人の存立根拠をなす天との関係性を「天」の側から言へば、それが「命」であり、「人」の側から言へば、それが「性」だといふことになる。ところが仁斎は、この「命」の語の用法を批判する。次に『語孟字義』を見てみよう。
『
經書連用する所天命の二字、天と命とを以て並べ言ふ者有り。天の命ずる所を以て言ふ者有り。其の天と命とを以て並べ言ふの命は、即ち性命の命、意重し。所謂五十にして天命を知る、及び死生命有り、孟子に曰く之を致すこと莫ふして至る者は命なりの類の若き、是なり。其の天の命ずる所を以て言ふ者は、即ち与ふる字の意。犹を孟子の所謂此れ天の我に予ふる所の者の予の字、意輕し。中庸に所謂天の命ずる之を性と謂ふ、是れなり。犹天の與ふる之を性と謂ふと曰ふがごとし。若し此の命の字を以て、性命の命と作して看るときは、則ち意義通ぜず。
』
(語孟字義)
「天命」と「天の命ずる」の二通りの用法がある、と仁斎はいふ。「天命」と並言される場合の「命」字のもつ意味は重く、それは「性命」の「命」の意である。「天の命ずる」といふ場合の「命」字の意味は軽く、それは「天の命ずるこれを性と謂ふ」の「命」の意である。そして「天命を知る」の「命」は勿論前者に属するといふ。仁斎は、文字には「実字」と「虚字」がある、と語の用法上の区別を説いていく。
『
盖し文字本實字有り虚字有り。性命の命は、是れ實字。天の命ずる所の命は、是れ虚字。先儒謬つて虚字を以て實字と作して看る、故に理の命、氣の命の別有り。又天に在つては命と為、人に在つては性と為るの説有り。皆中庸の命の字、本虚字實字に非ざるを知らざるが故なり。夫れ一の命にして二義を立つ、甚だ謂れ無し。況や虚字を以て實字と為、其の誤大なり。所謂其の説を求めて得ず、従つて之が辞を為す者なり。
』
(語孟字義)
仁斎の嗣子東涯は、『操觚字訣』で、「命ずる・見る・行く」の類は、「はたらきになる字」で「虚字」といふ。そして「天地・日月・命令」の類は、「実字」といふ。したがって「虚字」を用言、「実字」を体言として見ることが出来る。仁斎は、「命」字には体言的用法と用言的用法の別があり、『中庸』の「天命之謂性」の「命」は用言的用法だといふのである。ところが宋代の学者達は誤ってこの「命」字を体言として、「性命」の「命」と同意としてしまふことから、奇妙なこじつけともみなされるやうな理解が生じてゐるのだといふ。「命」の一字で二義があるといった説が生じるのは、語の用法上の別を無視することからくると仁斎はいふのである。
性理学(朱子学)では、「命」字が人における天との関係性を示す概念である。性理学的な言辞は、この概念の定義によって、また字義の解明によって、天との関係性に立つ思惟をたへず反復的に再生産するのである。これが性理学(朱子学)といふ同一的な思惟の展開であらう。
仁斎は「命」字の語法上の差異をつきつける。「命字に虚字あり実字あり」と。子安宣邦氏は、『天との関係性を己れの存立根拠とはもはやしない「人」が、仁斎の眼前に、或いはテクストの上に存在することになる。「人」が天との内在的な関係を離れる時、「天」とは己れの外に、己れに向き合ふ形で見出されてくる。』と解する。
かくて性理学的思惟に解体的に関はる仁斎の古義学は、「天」を、『論語』において仰ぎ見る、天を畏れ、自らをつつしむ孔子が見出され、人間孔子とともにあらためて己れもまた仰ぎ見る「天」として見出していくのである。
- ※参考文献
-
- 「子安宣邦著 江戸思想史講義」
- 「小島毅著 朱子学と陽明学」
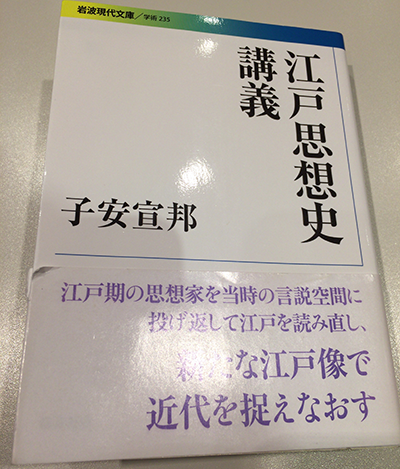

Leave a comment