本来民主主義とは、良しくも悪しくも、自由を守る為に導入された手段に過ぎなかった筈である。
だが、いつしか左翼勢力の台頭により、完全なる民主主義を実現することが至高の目的とされ、この目的を達成する為に、「自由にせよ、解放せよ」と、あくまでも手段として「自由」といふ言葉が使はれるやうになってしまった。
本来は、
[目的]
自由を守る
[手段]
各國の國體に従った手段がとられる。
民主主義制度は、その手段のうちの一つに過ぎない。
即ち、自由といふ至高の目的に、民主主義が必要ないのなら、必ずしもこの制度を導入しなければならないといふわけではない事になる。
ところが、二十世紀初頭から、左翼勢力の台頭により、目的と手段の倒錯が拡まるやうになる。
十七世紀末から十八世紀にかけて英國による高貴な自由、即ち自由主義が、西へ東へ新大陸へ、そして中央ヨーロッパへと拡大されていった。
だが、この思想は、十九世紀末になると退却を始め、これに代はるやうにして、全く異なる思想(実はそれは新しいものではなく、きはめて古い思想なのだが)が、今度は東方から拡がり始めた。社会主義の台頭である。この社会主義は、ドイツが思想の中心となり、やがてこの思想が東へ西へと拡がっていった。
では、この目的と手段の倒錯とはどういふ事か?と問はねばならなくなる。
目的が、完全なる民主主義で、その為の手段が自由だといふのなら、必ずしも「自由な社会」でなくともよい事になる、寧ろ自由主義を憎悪する社会にもなり得るのではないだらうか。
この点をハイエクは、このやうに述べてゐる。
『この「労働運動」といふ民主主義的運動が、民主主義それ自体を破滅へと導いていくのが必至な政策を支持したり、その間に、この運動を支持してゐる大衆のうち、ただ少数派の人々だけに利益を与へるやうになってきてゐるといふ現実は、我々の時代に生じてゐる最も嘆かはしい光景の一つである。
少なくともある程度まで、全ての働く人々に自主独立と自由を確保してきた唯一の秩序を破壊する事に、「労働運動」が手を貸し続ける限り、全くのところ、将来への希望は殆ど無い。「気違いじみた競争体制を完全に片付けてしまった」と、いまや大声をあげて宣言してゐる「労働運動」の指導者達は、個人の自由が破滅させられてしまった事を宣言してゐるのだ』
『主要価値としての民主主義が脅かされてゐるとばかり言ってゐるが、かういふ見方は危険を含んでゐる。このやうな考へ方は、究極的な権力のよってきたるところが多数派の意志である限り、権力は恣意的なものになる事はない、といふ人を惑はせる、根拠のない信念を生み出してきた主要な原因なのである。民主主義的手続によって与へられてゐる限り、権力は恣意的なものにはなり得ない、といふ信念は、どんな正当な根拠ももってゐない。権力が恣意的にならないやうにさせるのは、それがどこからきているか、といふ源泉ではなく、権力に対する制限なのだ。民主主義的な統制は、権力が恣意的になるのを防ぐかもしれない。だが、民主主義がただ存在してゐるだけでは、その防止が可能になるわけではない。民主主義が、確率したルールでは統御できないやうな、権力の使用を必然的に含む活動を行はうと決定するならば、間違いなく民主主義そのものが恣意的な権力となるのである』
(「F・A・ハイエク著 隷属への道(The Road to Serfdom 1944年)」)
ハイエクは、所謂自由放任は、自由主義にとって害であると云ふ。市場に於ける競争体制を守る為の秩序、即ち社会それ自体が持ってゐる自生的な力を最大限に活用し、そして強制は最小限に抑へるといふ事であり、競争が効率よく働くシステムを作る為なら、政府による最小限の介入を認めるものである。ここで大事な事は、「競争が効率よく働くシステム」を作る為の政府の最小限の介入であって、決して競争を阻害してしまふ介入は認めてはならない、といふ事である。
例へば、健康や労働能力を維持する為の最低限の食糧、住居、衣服を社会の全員に保障する事は、競争を阻害、破壊せず、寧ろこれによって、競争がより効率よく働ける場合に限り、可能であるといふ事なのである。
「社会それ自体が持ってゐる自生的な力を最大限に活用する」とは、即ち「法の支配」の事であり、ハイエクは、「法の支配とは、明確に決定され、前もって公表されてゐるルールの事であり、それらのルールは、長期的な規定である為、一体どういふ人々がそれによって利益を得るかが、決して分からないようなものであり、またさうであらねばならない」と云ってゐる。
さて、我が國のやうな伝統國家にとって、「法の支配」は、左翼思想に洗脳された現代日本において、最も見直さなければならないセオリーである。
法と法律は区別される。法とは、祖先から相続してきた伝統慣習の事であり、伝統慣習こそが不文の憲法なのである。
かくして、我が日本國は、「祖先から相続してきた伝統慣習」を遵守し、後世に受け継いでいく事で、真の自由が保障される。
- ※参考文献
-
- 「F・A・ハイエク著 隷属への道(The Road to Serfdom 1944年)」
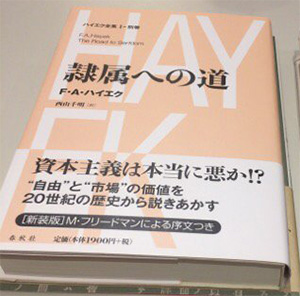
Leave a comment