昨今、我が國においても、「保守」なる言葉がよく聞かれるやうになった。
しかし実態は、保守といふ言葉だけが一人歩きしてをり、これでは左翼の手玉にとられてしまふ。
西洋哲学といふと、戦後の左翼教育を受けた現代の日本人は、「ルソー、ジョン・ロック、ホッブス、ケインズ、JSミル、マックス・ウェーバー、シュンペーター」等を思ひ浮かべるだらう。しかし彼らの思想は、反日思想そのものなのだ。
今から云ふ思想家、哲学者はご存知だらうか?
「エドマンド・バーク、トックヴィル、コーク、ハイエク、ハミルトン」
俺は、彼らを学校で学んだ記憶がない。
しかし、彼らこそ、真正保守(自由)主義の思想家、哲学者なのである。
次に大日本帝國憲法の起草者達を見てみる。
金子堅太郎はバークを日本に初めて紹介した。
井上毅はバーク抄訳を読みバークに感動した。
伊藤博文の座右の書は、ハミルトンらの「フェデラリスト」。
伊藤博文演説集-大日本帝國憲法とフェデラリスト
リバタリアンはまともな保守を支持する(5)エドマンド・バーク
以下引用
『・日本に初めてバークを紹介したのは金子堅太郎である。1881年、金子はバークの「フランス革命の省察」と「新ウィッグから旧ウィッグへ」を抄訳「政治論略」として元老院から刊行した。自由党のルソー主義への批判が目的であった。
・井上毅は、この金子のバーク抄訳を読みバークに感動し、金子を伊藤博文の秘書官に任用して、明治憲法の起草に参画させた。かうして、バークは明治憲法に影響してゐる。』
『明治天皇の詔命を奉じ、金子堅太郎、井上毅、伊東巳代治を統率して帝国憲法原案を起草した伊藤博文の愛読書は、明治三年に政況および財政調査のためにアメリカを訪問した伊藤に、当時のアメリカ国務長官ハミルトン・フィッシュが贈与したアメリカ合衆国憲法のコメンタリー(解釈書)「ザ・フェデラリスト」(一七八七年刊行)であった。伊藤博文は明治三年以来、このアメリカの古典的名著に依拠して憲法を研究し、彼ら四人が帝国憲法原案を起草してゐた時はもとより、明治二十一年から始まった枢密院帝国憲法制定会議の際にも、伊藤はフェデラリストを常に自分の座右に置いて何か問題が生じる度にこれを繰り返し読み、帝國憲法の制定に尽力したのであった。』
帝國憲法の中身は、國體(歴史伝統慣習)である。
帝國憲法の外枠は、「立憲主義」といふ構造になってをり、バークやハミルトンの真正保守主義に影響されてゐるのだ。
即ち、帝國憲法は、成文憲法であるから、「外枠と中身」の二つの面で、研究されなければならないと云ふ事なのである。
かういった真正保守(自由)主義の思想家のうち、エドマンド・バークを学ぶ事にする。
名著「フランス革命の省察」に学ぶ。
原著の刊行は1790年で、フランス革命の真っ只中においてである。
戦後の左翼教育では、フランス革命が神聖化される。
しかしこの本は、フランス革命を非難したものである。
それでは、「バーク著 フランス革命の省察」から、かの有名な「偏見」について書かれた箇所を紹介する。
『我々は一般に無教育な感情の持ち主であって、我々の古い偏見を捨て去るどころかそれを大いに慈しんでゐること、しかもその偏見がより永続したものであり、より広汎に普及したものであればある程慈しむのです。我々は、各人が自分だけで私的に蓄へた理性に頼って生活したり取引したりせざるを得なくなるのを恐れてゐます。我が國の思想家の多くは、共通の偏見を退けるどころか、さうした偏見の中に漲る潜在的智恵を発見するために、自らの賢察を発揮するのです。彼らは自ら探し求めてゐたものを発見した場合、偏見の上衣を投げ捨てて裸の理性の他は何も残らなくするよりは、理性折り込み済みの偏見を継続させる方が遥かに賢明であると考へます。何故ならば、理性を伴った偏見は、その理性を行動に赴かしめる動機や、またそれに永続性を賦与する愛情を含んでゐるからです。火急に際しても偏見は即座に適用できます。それは、予め精神を確固たる智恵と美徳の道筋に従はせておきます。そして、決定の瞬間に人を懐疑や謎や不決断で躊躇させたまま抛り出すことはしません。偏見とは人の美徳をしてその習慣たらしめるもの、脈略の無い行為の連続には終はらせないものなのです。正しい偏見を通して、彼の服従行為は天性の一部となるのです。』
「エドマンド・バーク著(半澤孝麿譯) フランス革命の省察 111頁」
[バーク保守主義の神髄]・保守主義とは、高貴な自由と美しき倫理の満ちる社会(国家)を目的として自国の歴史・伝統・慣習を保守する精神である。
・保守主義は、自由と道徳を圧搾し尽くす、全体主義(社会主義・共産主義)イデオロギーを排撃し殲滅せんとする、戦闘的なイデオロギーである。いざ戦時とならば、「剣を抜く哲学」である。
- ※参考文献
-
- 「エドマンド・バーク著(半澤孝麿譯) フランス革命の省察」
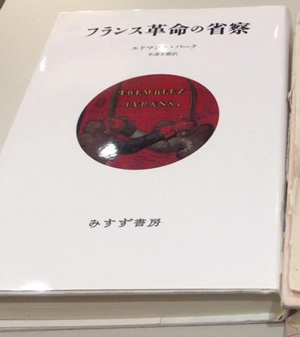
Leave a comment